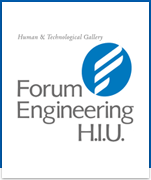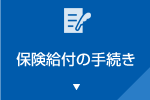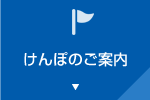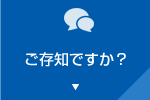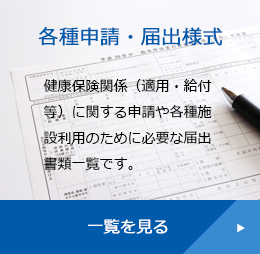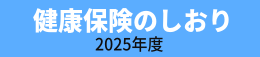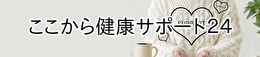保険診療をうけた被保険者・被扶養者ともに医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)以上になると、その超えた額が高額療養費として支給されます。この制度は患者の自己負担軽減を目的につくられています。
なお、自己負担限度額は70歳未満と70歳以上で異なります。
-

- ●
- 70歳未満の方で、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、申請により発行される「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
- ●
- 自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
高額療養費
医療費の自己負担額が診療(または調剤)報酬明細書(レセプト)1件※につき、下記の自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
さらに当組合では、独自の給付(付加給付)を上積みしています!
一部負担還元金(被扶養者の場合は家族療養費付加金)
診療(または調剤)報酬明細書(レセプト)1件※の自己負担額から20,000円を控除した額(ただし、高額療養費があるときは、それを控除した額から20,000円を控除した額(算出額が2,000円未満は不支給。100円未満は切り捨て)。
- ※
- レセプト1件とは、1人、1ヵ月、1医療機関単位です(同じ医療機関であっても、医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算となります)。
- ※
- 医療機関から交付された処方せんにより調剤薬局で調剤をうけた場合は、薬局で支払った自己負担額を処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。
- ※
- 入院時の差額ベットや食費の自己負担額など保険外診療分は対象外です。
- ※
- 手続きは不要です。医療機関からの請求書〔診療報酬明細書:レセプト〕に基づき、当組合で計算したうえで、医療をうけた月(該当月)の3ヵ月後(他の法令で公費負担をうける場合等や月遅れの請求分等を除く)に自動償還払いにより支給します。
自己負担限度額
70歳未満の方所得区分 適用区分 自己負担限度額 標準報酬月額83万円以上 ア 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 標準報酬月額53万~79万円 イ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 標準報酬月額28万~50万円 ウ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 標準報酬月額26万円以下 エ 57,600円 低所得者 オ 35,400円 - ※
- 低所得者とは、被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
- ※
- 所得区分は当組合の保険料月額表で確認ができます。
- ※
- 「適用区分ア」または「適用区分イ」に該当する場合、被保険者の市区町村民税が非課税等であっても、低所得者にはなりません。
自己負担限度額
70歳以上の方外来の場合は、まず個人単位での自己負担限度額が適用された後、世帯単位で合算します。入院を含む場合は、単身者でも世帯単位の自己負担限度額が適用されます。
平成30年8月診療分から 所得区分 自己負担限度額 個人ごとの外来 入院・世帯ごと 現役並み所得者Ⅲ
標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方252,600円+(かかった医療費の総額-842,000円)×1%
(多数該当の場合140,100円)現役並み所得者Ⅱ
標準報酬月額53~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方167,400円+(かかった医療費の総額-558,000円)×1%
(多数該当の場合93,000円)現役並み所得者Ⅰ
標準報酬月額28~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方80,100円+(かかった医療費の総額-267,000円)×1%
(多数該当の場合44,400円)一般所得者 18,000円
(年間14.4万円上限)57,600円
(多数該当の場合44,400円)低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 - ※
- 低所得者IIとは、被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
- ※
- 低所得者Iとは、被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
- ※
- 現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
合算高額療養費
高額療養費の自己負担限度額に達しなくても同一月に同一世帯でそれぞれ21,000円以上になった場合、これらを合わせて自己負担限度額を超えたときに合算高額療養費が支給されます。また同一人が同一月に2つ以上の医療機関にかかり、それぞれ21,000円以上になった場合も同様です。
さらに当組合では、独自の給付(付加給付)を上積みしています!
合算高額療養費付加金
合算した自己負担額より、合算高額療養費に相当する額を控除した額から、1人につきそれぞれ20,000円を控除した額(算出額が2,000円未満は不支給。100円未満は切り捨て)。
多数該当
同一世帯で4カ月目からはさらに軽減同一世帯で1年間(医療をうけた月以前の12ヵ月間)に3ヵ月以上高額療養費が支給されている場合に4ヵ月目からは以下のように自己負担限度額が変わります。
- ※
- 多数該当は同一保険者での療養に適用されます。他の保険から当組合の保険に加入した場合など、保険者が変わったときは多数該当の月数に通算されません。
所得区分 適用区分 自己負担限度額 標準報酬月額83万円以上 ア 140,100円 標準報酬月額53万~79万円 イ 93,000円 標準報酬月額28万~50万円 ウ 44,400円 標準報酬月額26万円以下 エ 44,400円 低所得者 オ 24,600円 - ※
- 低所得者とは、被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
- ※
- 所得区分は当組合の保険料月額表で確認ができます。
- ※
- 「適用区分ア」または「適用区分イ」に該当する場合、被保険者の市区町村民税が非課税等であっても、低所得者にはなりません。
限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証について
保険医療機関等の窓口において高額な医療費を支払った場合は、自己負担限度額を超えた分について、「高額療養費」として支給されます。しかし、70歳未満の方で適用区分がア・イ・ウ・エに該当する場合、事前に「健康保険限度額適用認定申請書」の届出をすることにより発行される「健康保険限度額適用認定証」と被保険者証(保険証)を併せて保険医療機関等の窓口に提示することで、窓口での負担が自己負担限度額までとなります。
また、被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合(適用区分がオに該当する低所得者の場合)は、事前に「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に被保険者の非課税証明書を添付のうえ、届出をすることにより発行される「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」と被保険者証(保険証)を併せて保険医療機関等の窓口に提示することで、窓口での負担が自己負担限度額までとなります。- ※
- 交付された認定証を医療機関等の窓口に提示しなかった場合および事前申請をされなかった場合は、従来通り3ヵ月後に自動償還払いにより支給することになります。
- ※
- この制度は、高額療養費(法定給付)のみに適用されるため、付加給付(組合独自給付)の支給は、従来通り3ヵ月後に自動償還払いにより支給することになります。
特定疾病療養受療証(腎透析患者と血友病患者の自己負担限度額:高額療養費)
人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)の患者ならびに血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(血友病)の患者および抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者にかかるものに限る)の患者は、所定の手続きをすると長期高額疾病として自己負担限度額が10,000円(月額)となります。ただし、人工透析を要している70歳未満の上位所得者(標準報酬月額53万円以上で基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方)は、自己負担限度額が20,000円(月額)となります。
- ※
- 「血友病患者の自己負担限度額は10,000円(月額)ですが、公費負担があり、事実上自己負担(窓口負担)はありません。
高額介護合算療養費
世帯内の同一の医療保険(健康保険、国民健康保険、船員保険、共済組合等)の加入者の方について、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計(合算額)が基準額を超えた場合は、「高額介護合算療養費」が支給されます。
支給要件
当組合加入の被保険者およびその被扶養者において、同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、健康保険と介護保険の両制度ともに自己負担額※があり、その自己負担額※の合計額が下表の基準額を超えたとき、被保険者からの申請に基づき支給されます。
- ※
- 高額療養費、付加給付(一部負担還元金・家族療養費付加金)、高額介護サービス費等は自己負担額から控除します。
- ※
- 入院時の食事代・居住費・差額ベッド代等は含みません。
- ※
- 支給額(基準額を超えた額)が500円以下の場合は、不支給となります。
- ※
- 低所得者IIとは、被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
- ※
- 低所得者Iとは、被保険者とその被扶養者全ての方の収入から、必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。
基準額
所得区分 70歳未満の基準額 70歳から74歳の基準額 平成30年7月まで 平成30年8月から 標準報酬月額83万円以上 212万円 67万円 212万円 標準報酬月額53万~79万円 141万円 67万円 141万円 標準報酬月額28万~50万円 67万円 67万円 標準報酬月額26万円以下 60万円 56万円 低所得者II
(住民税非課税)34万円 31万円 低所得者I
(年金収入80万円以下等)34万円 19万円 -
医療費の窓口負担を減らしたいとき
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証厚生労働大臣の定める疾病医療費の窓口負担を減らしたいとき
特定疾病療養受療証医療と介護の自己負担が高額になったとき
高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書こんなときに、こんな届出を !
外傷性によるケガをされた場合
他人の加害行為により病気やケガをされた場合
-